「貴船さんと話していると、忘れていたことを思い出しますね。」
「そう?」
「ええ。でもこれって…。」
「何?」
「思い出しても大丈夫になったからなんですねぇ。」
「なんだい、しみじみと。」
貴船オーナーは下げてきたばかりのカップを丁寧に洗いながら声だけで答えている。
その気安さが嬉しい。
小さく揺れるオーナーの背中を見ていると、僕は本当に幸せなんだよなと改めて思う。
「病気が分かった時も、姉さんが日本を出たときも、あの教育実習も、その場その場ではショックで傷ついたりもしたけど、僕にはいつでも心強い味方がいて、安心できる居場所があったなぁと。
だから、ちょっとぐらい痛くても大丈夫だと思えるんだぁって。
で、実際、心の傷はいつの間にかふさがっていて、思い出しても痛まなくなってる。
それって、幸せなことですよね。」
最後の水滴を拭き上げたオーナーは、カップとソーサーを丁寧に棚に戻すと、ふふんと鼻を鳴らしながら笑った。
「そういうことを改めて言葉にされると、なんとも尻がくすぐったいというか、照れくさいものだなぁ。
でも、その通りなんだろうね。」
「青年!」
オーナーの声にかぶさるように、背後から突然声をかけられて、僕は呼ばれたからというより驚いて、振り向いた。
そこには先ほどまで深刻そうな話をしていた、今では女子高生のようにはしゃいでいる二人の妙齢の女性がいた。
「ぼくですか?」
「そう。悪いけど、話が聞こえちゃって。」
「すみません、うるさかったですね。」
「そうじゃないわよ。あなた、いいことに気付いたじゃないの!」
「はぁ、そうですか?」
「そうよ。若いのに、なかなかいいじゃない。」
「はぁ、ありがとうございます。」
掛け合い漫才のようなテンポの良さに押されて、ついお礼まで言ってしまった。
「今の自分の幸せに気付きながら生きるのは、きっと幸せな人生の近道よ。」
「そうそう。私なんか、日ごろの忙しさや目先のイライラに惑わされて、本筋をすぐ忘れちゃうもんねぇ。」
「それって、そもそも忘れやすい歳になったってことでしょ?」
「あら、そうかしら。」
「さっき、自分で言ってたじゃないのぉ。もう忘れたの?」
「あらぁ、ほんと、忘れちゃったわ。あはは。」
自分はいら立ちのあまりに、利用者さんを殺してしまうのではないか。
この、こちら側の人は、そんな話をしていたのだ。
でも、今はすっかり忘れたのか、肚の底から笑っている。
ここ『ルナソル』でのひと時が、この人の心にそよ風をもたらしたことは疑いない。
「ここはいいですね、貴船さん。」
「僕が心血注いでいる店ですから。」
「じゃ、今日はこれで帰りますけど、よかったら僕の店にも来てください。」
「もちろんうかがうよ。」
僕はその返事を聞きながら、こんな時のために、いつも財布に入れて持ち歩いている名刺をオーナーに手渡した。
「へぇ、穂高くんか。」
「ええ。僕も源氏名をもらいましてね。今ではホタカと呼ばれる方が断然多くて、どっちが本名か分からないくらい馴染んじゃいました。」
そうして、僕はオーナーにしか聞こえないくらい声を潜めて頼んだ。
「すいませんけど、何か書くもの貸してください。」
僕の意を察したらしいオーナーは、注文をメモするためのボールペンを胸元からさっと出して貸してくれた。
木目の美しい軸のペンだ。
こういうところまで100円均一にしないところが貴船たるゆえんなのだろう。
ヘンなところに関心しながら、僕はもう一枚の名刺を裏返して書き込んだ。
素晴らしい笑顔のお二人へ
今日の出会いが次に続きますよう
これをお持ちいただいたら、
お二人にお似合いのカクテルを1杯ずつ
サービスさせていただきます。
幸せに気付いた青年より
オーナーにペンを返し、席を立つと、僕は二人の女性に向かってその名刺を差し出した。
「よかったら、次回はこちらにいらしてお話しなさってください。」
目を丸くした熟女たちは、名刺の裏を読むと歓声をあげた。
「ほんとにプレゼントしてくれるの?」
「はい、もちろん。お待ちしています。」
「もう、絶対行っちゃう!だってここ、案外近いじゃない!」
貴船オーナーに会釈して店を出た。
来た時以上の暑さが、ドアの外に広がっている。
ゆかりさんの家の庭に干したタオルケットとシーツを思い出す。
これならば、もうすっかり乾いたに違いない。
電車を降りてゆかりさんの家に向かう。
この道を歩いていると、ここが僕の居場所なんだなと、じわりじわりと安心感が広がっていく。
ルナソルも好きだけど、僕のホームタウンはここなんだ。
普段よりも宙に浮いている時間が少し長いかもしれない速足で、僕はゆかりさんの家に向かった。
「ゆかりさん、早く帰ってこないかな。」
5日間の北海道旅行にでかけたゆかりさんが帰るまで、あと2日ある。
自由人だから、「ちょっと延長ね」と連絡が来ても何の不思議もない。
別にいないと困るわけではないけど、仕事が休みだと、なんだか手持無沙汰だ。
ゆかりさんの家が見えてきて、僕は首をかしげた。
庭が見えるけど、洗濯物が見えない。
あれ?風に吹き飛ばされてしまったのかな?
それほど強い風が吹いたとは思えないけどといぶかしがりながら、僕は駆け出した。
「やっぱり、ない!」
庭に飛び込み、きょろきょろする。
洗濯カゴは置いた場所にそのままあるのに…
その時だった。
「穂高、ただいま!」
「ゆかりさん!!」
庭に面したガラス戸がガラリと開いて、ゆかりさんが全身を見せた。
「帰ってきていたんですか?あと2日残っていたでしょ?」
「それがね、聞いてよ。」
ゆかりさんはおいでとも言わないけれど、僕は縁側からゆかりさんのうちに勝手に入った。
それを咎めもせずに、ゆかりさんは旅が短くなった顛末を話している。
ふと見ると、畳の部屋にはアイロン台が出してあって、僕のシーツが半分、一つのしわもなく平らになっているところだった。
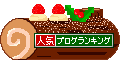
人気ブログランキングへ

コメント
コメント一覧 (2)
傷ついたときは、このまま永遠に痛いままだと思います。
でも、次の日にはだいぶ薄れ、その次の日にはなくなってしまうことが多いです。
自分の味方がいるかどうかも大事ですね。
たとえ、周りが敵ばかりでも、「あの人だけは自分を裏切らない」という相手がいると、防護壁ができますし。
幸せは、身近なところにあります。
それに気づくかどうか、それだけなのではないかしら。
人は見たいものを見るそうです。
幸せを見たいと思っていれば、いずれそれが見えるのでしょう。
でも、不幸の原因は何?とばかり思っていたら、不幸の原因ばかりが見えるということでもありますね。
あのイヤな出来事は気づきのために必要だったのだと思えたら勝ったも同然。
そういう人は魅力的だから、周りに信頼できる人がますます集まるでしょう。
がんばれ、穂高くん!