姉さんが送ってくれたコーヒー豆を抱えたまま、ぼんやりとあの頃のことを思い出していた僕は、母さんのことにたどり着いた途端に、ふっと現実に戻った。
ひとつ頭を振ってから立ち上がり、台所に置いてあるコーヒーミルを取りに行く。
僕のコーヒーミルは木製の手動式で、カリカリと優しい音をさせながら、1杯分の豆を挽くのに丁度いい。
途中、目に入った窓の外は、やっぱり雨が降っている。
コーヒーは空気に触れさせるとすぐに酸化するから、封を切ったらすぐに密閉容器に移すようにと姉さんから教わった。
それほど大きくない袋を切り、すぐに瓶に移してふたを閉めた。
そうして、1杯分の豆だけをミルに入れて、 左手でしっかり押さえると、小さなハンドルをくるくるとゆっくり回し始める。
荷物をほどいた時よりも鮮やかな香りが立ち上ったから、思い切り吸い込んでみる。
えも言われぬ芳香に、吸った息がほうっとため息になってこぼれる。
母さんの命を奪ったのは、くも膜下出血だったそうだ。
倒れている母さんを見つけたのは会社の人だった。
僕が家を出たあの朝、母さんは会社に行くと言っていたが、実際には出社しなかったという。
そんなことは一度もなかったから、不審に思った会社の人が電話をくれた。
母さんは、電話に出なかった。
昼休みに、母さんと特に仲が良かった事務の人が、すぐ近くだからと家を訪ねてくれた。
そこで、倒れている母さんを見つけたのだ。
すでに意識はなく、意識を取り戻すこともなかったと聞いた。
姉さんはあれでも、僕がいつ家を出るかをよく分かっていて、母さんが寂しくないようにと、同じ日の夕方に帰宅したのだそうだ。
そういう心遣いが姉さんらしい。
でも、待っていたのは隣の部屋のおばちゃんたちの「大変だよ!」で、姉さんは慌てて救急車が母さんを運んだ病院へ駆けつけた。
その時にはすでに、母さんは帰らぬ人となっていたのだ。
それから姉さんは、僕を探した。
けれどもまだ入学式の前で、僕は借りた部屋のことを大学へは届けていなかった。
ついでに、今夜連絡するからと気軽に約束して放っておいたほど、何も考えていなかった僕は、母さんにも姉さんにも、新しい部屋の住所を伝えていなかったのだ!
入学式にはやってくる母さんを東京駅まで迎えに行くつもりでいたし、その時には当然住所もなにも分かるわけで、わざわざメモを置いておくなど考えもしなかった。
だから、姉さんは僕を見つけられず、ひたすら僕からの連絡を待つしかなかったのだ。
姉さんはそうやって、5日も僕を待ったのだ。
怒鳴られて泣かれて、当然だった。
いくらなんでも、亡くなった人を5日も放ってはおけず、今夜には通夜をしてやろうということになったのだと言われて、僕は跳ね上がった。
そのまま、近くにあったカバンをひっつかみ、その日買って、今切れたばかりのケータイは握り締めたものの、玄関のカギを閉め忘れたまま故郷へ戻った。
かりかりかりかり。
ゆっくりと手を動かしていると、記憶が遠くへ飛んでしまう。
できたかな。
小さな引き出しには、細かな粒に…僕は粗びきが好きだ…なったコーヒーたちが、さあお次へどうぞと待っている。
もう一度立ち上がって、台所へ行く。
湯を沸かすあいだに、フレンチプレスを用意する。
これは多分、紅茶を淹れるための道具だ。
でも、姉さんが、これが一番美味いのだと教えてくれた。
ペーパーフィルターは、紙の質しだいで、実はコーヒーににおいが移っていることがある。
サイフォンは楽しいが、布フィルターを常に清潔かつ濡らしておかねばならず、素人には扱いがむずかしい。
その点、フレンチプレスは、コーヒー本来の味が楽しめるからいいのよ。
沸騰した湯を、一息おいて注ぐ。
腕時計で3分計って、丸い取っ手をじっくりと下へ押し下げる。
余った湯で温めておいたカップにすぐ、ざらざらした粉が移らないよう気を付けながら、そっと注ぐ。
注ぎ切らないのが秘訣だ。
そうやって淹れたコーヒーを片手に、僕はリビングに戻る。
一口。
砂糖もミルクも入れていないのに、甘みのある深い味わいが体中の細胞に沁みるような気がする。
姉さんのコーヒーはやっぱりうまい。
あの日、5日ぶりに開ける玄関のノブを引いたと同時に、姉さんが顔を出した。
そうして、鬼のように真っ赤な顔をして、思い切り、僕の頬を平手打ちした。
バッシッ!
本当に、本当に、本当に痛かった。
目玉が火の粉を散らして飛び出し、玄関の外のコンクリートに転がり落ちたのではないかと思った。
立っていられず、頬を押さえてその場にしゃがみこんだ僕の頭を、上からもう一発バシッとたたいた姉さんの、はだしのつま先が見えた。
「自分が待たれていることに鈍感な男は、大っ嫌い!」
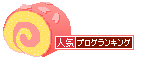
人気ブログランキングへ

コメント
コメント一覧 (4)
苦しむことはなかったのかしら。
元同僚も、くも膜下出血で亡くなりました。
残された者にとっては、突然すぎて、ただ呆然とするだけ…。
平手打ちの激しさが伝わってきます(笑)
姉さんの手のひらも、痛かったでしょうね。
くも膜下出欠から生還された方に聞いても、
とてつもない頭痛がした後は記憶がないとおっしゃいます。
突然のことに、周囲もご本人も驚くしかできないですね。
平手打ちの激しさ、伝わりましたか!
叩いた方が、叩かれるより痛いと聞いたことがありますが、やっぱり、やられた方が痛いと思う。
姉さんのてのひら、きっと真っ赤です。
コーヒー好きだから、わかります。
ズーット、弟からの電話を待つしかなかった、お姉さんは、
つらかったでしょうね・・・
置いて行くのと待つのと、どちらが辛いか、という話が平家物語にも出てきます。
行くのも帰るのも選べる身と、待つしかないのとを比べてしまうと、待つ方が辛そうです。
コーヒーは豆と水が織りなす芸術だ!なんて思うほど美味しい時があります。
あの茶色の液体にそんな魔力があると気付いた人はすごかったですね。