「穂高くん、今度の日曜日、空いていますか?」
唐突な質問の主は宮田医院の先生だった。
「は?」
「朝から晩まで、みんなで恒例の花見なんですよ。一緒に行きましょう。」
「花見ですか。用事も予定もありませんが。」
「よしよし。じゃ、今年は6人ということで。元さん、車出してくれるだろうね?」
「そりゃもちろん。ただし、助手席は…。」
「分かってるって。ママに座ってもらえばいいんだろ?」
徳さんがしたり顔に受けた。
気象庁の開花宣言から2週間、花見にしては少し遅いような気がする。
街はすでにどこもかしこも桜色に染まっていて、強い風が吹くと、花弁が雪のように降り注いでくる。
風は確実に暖かさを増した。
僕が一年で一番好きな季節だ。
冬が春になる変わり目を見逃した今年の僕でも、この花の美しさとはかなさは見逃しようがなかった。
常連さん方はグラスを持つのも忘れたように4人で額を突き合わせて、あーだこーだと盛り上がっている。
そういえば、日曜に行くとは聞いたが、どこへ行くかは聞いていない。
それとも、まだ決まっていなくて、今あそこで相談しているのだろうか。
すぐにも知りたかったのだけれど、僕は質問を禁じられている。
伝えてもらえるまで、心待ちに待たなくてはならなかった。
それが分かったのは、水曜の営業が終わった後だった。
「そうそう、穂高。今度の日曜日はお店をお休みしてお花見に行きますよ。」
「ああ、はい。僕も誘ってもらいました。元さんたちと一緒ですよね。」
「そうよ。毎年の決まりごとのようなものなの。車で出かける前に支度をしたいから、朝早くからになって悪いけど手伝ってもらえるかしら?」
「わかりました。ところで、どこに行くんですか?」
「今年は山梨だそうよ。」
「山梨!」
車でというところは聞いていたのに、僕はなんだか上野や皇居の周り、隅田川沿いなどの夜桜をイメージしていた。
「けっこうな人出になるから、朝早く出るのよ。」
「だったら平日にしたらいいのに。
みんな自由業みたいなものだから、どうにでもなるんじゃありませんか?」
「確かにね。でも、宮田先生は違うわ。
先生は夜と木曜日の午後と日曜日しか休まないの。
木曜の午後は学会だから、本当のお休みは日曜日しかないのよね。」
なるほど。
「もっとも、先生は『俺が休んでも周りにはいい医者がいくらでもいるから患者は困らないよ』なんて言うんだけどね。
でも、かかりつけのお医者様が頼りたいときにいてくれるかどうかって大きいでしょう?
先生はそれをよく分かってくださっているの。
ありがたいことよね。」
それを聞いたら、人混みが苦手だから平日がよかったなどと、迂闊な愚痴を言わなくてよかったと胸をなでおろした。
こんな時だ。
僕は自分がちょっと嫌になる。
いつも自分のことばかり考えていて、相手の深い思いに気付かない。
自分の都合で簡単に判断して、後からしまったと思うことばかりだ。
「山梨のどこですか?」
「私ね、詳しく聞かないことにしているの。」
「えっ?どうして?」
「ささやかな、いたずら。」
「いたずら、ですか?」
「そう。自分に対していたずらするの。」
「意味がわかりません。」
「いいのよ、分からなくて。」
「でも、スッキリしないですよぉ。」
「しょうがないわね。穂高は、知らないことをする時って、どんな気持ちになる?」
「知らないことですか?そうだなぁ。見通しが持てないと不安です。」
「そうなの。じゃ、ここ最近、毎日不安でしょうね?」
「はぁ。確かに。でも、だいぶ慣れてきたから、不安もあまり感じなくなってきましたよ。」
「じゃぁ、その見通しの持てない先に、何かとっても素敵なものがあるとしたら?」
「あらかじめステキなことだと分かっているってことですか?」
「そう。贈り物がもらえる。それが何かはわからない。 でも、絶対にもらえるの。それなら?それでも先に中身が分かっていないと不安?」
「いや、そんなことはないです。うーん、でも、どうかな。実はステキなものじゃないかもしれないわけですよね?」
ゆかりさんは片付けの手を止めて、僕の顔をじっと見つめた。
いつも朗らかなゆかりさんの顔に表情がなくなっていて、僕はぞくっとした。
「なんですか?」
「穂高って、人を信用していないのねー。」
「は?」
「贈り物を上げるよって言われたら、わーありがとう、何だろうなぁワクワク、って思いそうな顔していながら、実は、いや待てよ、そんなうまい話があるんだろうかって考えているなんて。人を信用していない証拠だと思わない?」
思わない?と言われると、そんな気がしてきた。
そうしてそれがバレたことが後ろ暗くて、なんだかムクムクと嫌な気持ちが湧きたってくる。
そんな僕に、ゆかりさんは助け舟を出してくれた。
「ま、都会で生きていくんだから、それくらい慎重な方が騙されなくていいかもしれないけれど。」
「そ、そう。僕は慎重なんですよ。」
僕は、その時気が付いた。
ゆかりさんは、いつも逃げ道を塞がずにいてくれる。
だから、安心して話せるのかもしれない。
育ちがそうなのか、元々の性格なのか、それともこの仕事をするうちに培った技術なのか。
ゆかりさんは決して相手を言い負かそうとしないから、言い争いにならない。
お客様たちも、僕も、それが心地よいのだろう。
「わかりました。ゆかりさんは、贈り物がどんなものが、自分の目で見るまでバラさないでおいてほしいわけですね?」
「そうそう。そういうこと。だって、その方が嬉しさが増すんですもの!」
少女のようだなと思う。
60歳を過ぎて少女のような心なんて不気味そうだけど、決してそうではない。
僕は、実はすごい人に出会ったのかもしれなかった。
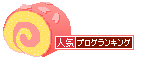
人気ブログランキングへ

コメント
コメント一覧 (2)
明日はランチ&マグリット展です。
近場にお花見スポットあったかしら。
皇居の桜は好きだけど、上野はごった返しているし目つきの悪い人が多くてイヤだな。
山梨ならば、ゆったりできてよさそうですね。
私も行きたい(笑)
マグリット展のご報告を楽しみにしています。
以前からとても刺激を受けている画家です。
我が家の明日は東博でみちのくの仏様に会いつつ、桜を満喫しようかと。
平日の昼間でも、ごった返しているのでしょうか。
山梨は、桜も桃もオススメです。
今年も行くぞ〜!