「幸吉さん、幸吉さん、この植木鉢を玄関に並べたいから、手伝ってくださいよぉ。」
真理に呼ばれた幸吉じいさんは、よたよたと歩いて真理の横にたどり着いた。
「重たいですか?大丈夫?」
色とりどりのパンジーが咲いた植木鉢の中から、真理は黄色と紫が鮮やかなひと鉢を選んで幸吉じいさんに手渡しながら、その顔を覗き込んだ。
「だいじょうぶだよぉ、心配いらん。」
レコードを回転数を落として再生したような間延びした声で答えた幸吉じいさんは、手渡された鉢を大事に腹に抱えると、元来た方向に歩きだした。
「ちがう、ちがう。玄関だってば!そっちはトイレでしょ!?」
「お?トイレにきれいな花を飾るんじゃなかったかいね?」
「だからぁ、玄関だってばぁ!」
そのやりとりを聞きながら、お日様がさんさんと当たっている玄関わきで、梅ばあちゃんや亀ばあちゃんが大笑いしている。
ばあちゃんたちを手伝って、ミドリが今こしらえているのは、味噌餅だ。
「ミドリちゃん、もっと早く手を動かして。かたまってしまうよぉ。」
「はい、どんどん。」
ばあちゃんたちは口だけが早くて、手は動かしていない。
指揮官たちの応援に応えるべく、ミドリは必死に手を動かしている。
味噌が餅にまざらない。
「ああ、もう、貸してごらん。」
とうとうしびれをきらせた亀ばあちゃんがミドリから木べらを奪って臼の横に陣取った。
ミドリは汗を拭きながら目を見張る。
どれだけ力を入れても味噌と餅はマーブル状にしかならなかったのに、亀ばあちゃんの手にかかると、みるみるキャラメル色の滑らかな艶が広がっていく。
「すごいわぁ。」
ミドリが感嘆の声をあげると、梅ばあちゃんのほうが、ふふんと小鼻を膨らませて答えた。
「亀さんの味噌餅は絶品だからねぇ。ミドリちゃんはまだまだだぁ。」
そこへ福ばあちゃんがサンダルを履くのももどかしげにパタパタパタとやってきた。
「ほれ。クルミが刻めたよ。間に合ったかね?」
「福さん、丁度いい時に来たねぇ。さ、入れとくれ!」
亀ばあちゃんが手を休めずに言うと、ボールいっぱいに入っていた刻みクルミが臼の中に投入された。
「わぉ〜っ。美味しそう!」
ミドリの歓声につられて、玄関掃除をしていた何人かが、臼の方へと集まっていった。
そこへ福ばあちゃんがサンダルを履くのももどかしげにパタパタパタとやってきた。
「ほれ。クルミが刻めたよ。間に合ったかね?」
「福さん、丁度いい時に来たねぇ。さ、入れとくれ!」
亀ばあちゃんが手を休めずに言うと、ボールいっぱいに入っていた刻みクルミが臼の中に投入された。
「わぉ〜っ。美味しそう!」
ミドリの歓声につられて、玄関掃除をしていた何人かが、臼の方へと集まっていった。
玄関の並びにある部屋では、庭に出るためのドアを開け放したまま、ひとつの机に向かい合わせて額を寄せている二人の姿が見えている。
「で?隆三おじさん、どうしてそういうことになるわけ?」
「つまりだなぁ、こことここが共通だから、こうまとめてだなぁ…カッコの中にこことここを書くんだな。」
「あーもう、わからない!マリアンヌ!数学教えて!」
「待て待て、スミレちゃん。もう少し聞いてくれたらわかるって。」
「ありがとう、ありがとう。もう、大丈夫だよぉ〜!」
教えたがる隆三おじさんに作り笑顔を見せたスミレは、手早くノートと教科書を閉じると、がさっとひと抱えにして逃げ出した。
呼ばれたマリアンヌはリハビリ指導の最中で、数学どころではない。
「トメさん、いいわよ。だんだん筋肉がついてきている。もう少し膝をあげられる?そうそう。いい感じ!」
「ほほほっ。わしゃもう一度元気に歩けるようになって、じいさんにかたき討ちするんじゃ。」
「えっ!?おじいさんのかたき討ち?」
トメばあちゃんはリハビリが続けられないくらい大笑いしてから言った。
「違うよ。じいさん『に』かたき討ちじゃ。じいさんときたら、わしが歩けなくなったのをよいことに、わしを家に残して、あんたさんに毎日会いに来とったろう。いやらしいじいさんだ。だからわしゃこうして、あんたさんにひっついて、嫌がらせをしとるんじゃ。そうしてせいぜい元気になって、男前を探しに行こうと思ってねぇ。」
「やだ、もう。ほらほら、休まないで。で、トメさんはどんな男性が男前なの?」
「そりゃもう、じいさんほどの男前はおらん。」
「は〜ごちそうさま。リハビリの回数増やしちゃおうかなぁ。」
「ほい?」
マリアンヌに促されて、トメばあちゃんは、白いバーを両手で一つずつ握った姿勢で、再びよっこいしょと膝を持ちあげた。 「そりゃもう、じいさんほどの男前はおらん。」
「は〜ごちそうさま。リハビリの回数増やしちゃおうかなぁ。」
「ほい?」
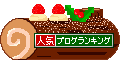
ポチッと応援お願いします

コメント
コメント一覧 (2)
良くないそうですね
アンモニア気体があるのですから、当然といえば当然です
代わりに造花を置いたらどうでしょうと言いましたら年配の女性に
造花は死んだ花だから
家には置かないほうがいいと教えていただきました
トイレにグリーンはいいですよね。
私は造花だからとか拘らず、季節ごとのリースを飾ったりして楽しんでいます。
今はもちろんクリスマス仕様。
同居者に「プレゼント募集中」のメッセージなのですが
届いているかしら?
そのうち素敵なものに出会ったら、実力行使するんですけど(^0^)